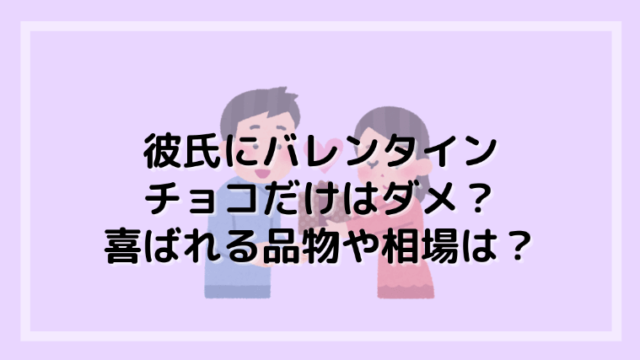初節句のお返しマナー完全ガイド!親戚への感謝の気持ちを込めた贈り物と適切な時期
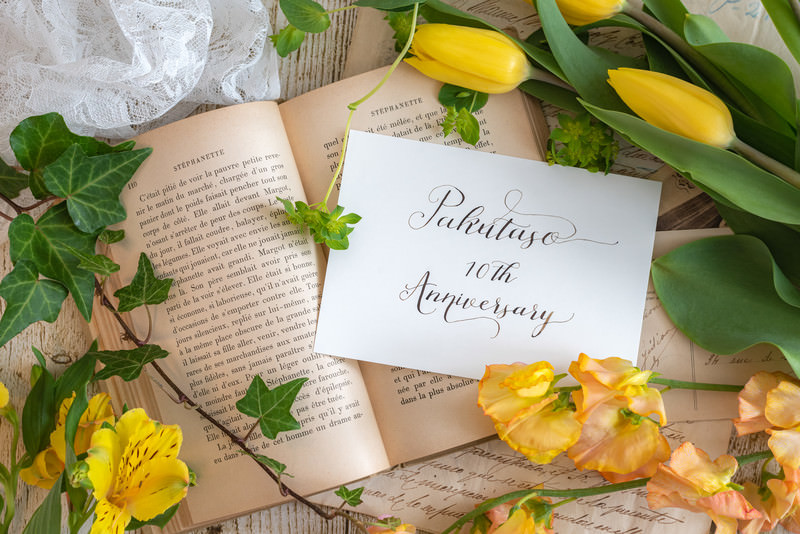
お子様の初節句、おめでとうございます!
親戚の方々からお祝いをいただいて、嬉しい反面「お返しはどうしたらいいの?」と悩んでいませんか?
実は私も長男の初節句の時、親戚から立派な五月人形をいただいて、お返しの相場や時期について夜中にスマホで検索しまくった経験があります。
特に義理の両親や親戚との関係を考えると、失礼のないようにしたいですよね。
この記事では、初節句のお返しで押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。
相場や時期、選び方のコツまで、実体験を交えながらお伝えしますので、安心してお返しの準備を進められますよ!
初節句のお返しとは?基本的なマナーと意味を理解しよう

初節句のお返しは、お祝いをいただいた方への感謝の気持ちを表す大切な習慣です。
でも実は、地域や家庭によって考え方が違うんですよね。
まずは基本的な知識を身につけて、自分の状況に合った判断ができるようになりましょう。
最近では昔ほど厳格ではありませんが、やはり親戚関係を円滑に保つためにも、最低限のマナーは知っておきたいものです。
初節句お返しの由来と現代での意味
初節句のお返しは、もともと江戸時代から続く日本の伝統的な習慣なんです。
当時は、お祝いをいただいた家が「内祝い」として親戚や近所の方々にお赤飯やお菓子を配って、喜びを分かち合っていました。
現代では、この習慣が少し形を変えて「お返し」という形になっているんですね。
つまり、お祝いをいただいた感謝の気持ちを形にして表現するのが、現代の初節句お返しの意味なんです。
私の祖母から聞いた話では、昔は近所中でお祝いしていたそうですが、今は核家族化が進んで、主に親戚間でのやり取りが中心になっています。
でも、感謝の気持ちを表すという基本的な意味は変わりませんよね。
現代のお返しには以下のような意味が込められています。
- お祝いをいただいた感謝の気持ち
- 子どもの成長を一緒に喜んでもらえた嬉しさ
- 今後もお付き合いをお願いしたいという気持ち
- 家族としての絆を大切にしたいという想い
お返しが必要な場合と不要な場合の判断基準
「そもそもお返しって絶対に必要なの?」って疑問に思いますよね。
実は、お返しが必要かどうかは、いくつかの要因によって判断が分かれるんです。
お返しが必要な場合は、主に以下のようなケースです。
- 親戚から高額なお祝い品(1万円以上)をいただいた場合
- お食い初めや初節句の食事会に参加してもらった場合
- 地域の慣習でお返しが一般的とされている場合
- 今後の親戚付き合いを考慮して、関係を良好に保ちたい場合
一方、お返しが不要とされることもある場合もあります。
- 祖父母からのお祝い(孫への愛情表現のため)
- 少額のお祝い品(3000円未満程度)
- 食事会でのおもてなしがお返し代わりとなる場合
- 相手から「お返しは不要」と明確に言われた場合
私の経験では、義理の両親には「お返しは気にしないで」と言われましたが、やはり何かしらの形で感謝を表したほうが、その後の関係がスムーズになりました。
迷った時は、お返しをする方を選ぶのが無難ですね!
地域による初節句お返しの慣習の違い
日本は地域によって、初節句のお返しに関する慣習が結構違うんです。
結婚して初めて知って驚いた方も多いのではないでしょうか?
私も主人の実家がある関西と、私の実家がある関東で、全然習慣が違って戸惑いました。
関東地方の特徴:
- お返しの相場は比較的控えめ(いただいた金額の1/3程度)
- 品物よりも商品券やカタログギフトが好まれる傾向
- お返しの時期は初節句から1ヶ月以内が一般的
関西地方の特徴:
- お返しを重視し、しっかりとした品物を選ぶ傾向
- 老舗の和菓子や伝統的な品物が好まれる
- のしや包装にもこだわりを持つ家庭が多い
九州地方の特徴:
- 親戚一同でお祝いする文化が根強い
- 食事会を開くことがお返しの意味を持つことも
- 地域の特産品をお返しに選ぶ家庭が多い
もし配偶者の実家の地域と自分の実家の地域で慣習が違う場合は、事前に両方の家族に相談して、どちらの慣習に合わせるか決めておくと良いですね。
私は結局、両方の慣習を取り入れて、少し大変でしたが、どちらの家族にも喜んでもらえました!
親戚への初節句お返しの相場と選び方のポイント

お返しの相場って、一番気になるポイントですよね!
高すぎても相手に気を遣わせてしまうし、安すぎても失礼になってしまいます。
ここでは実際の相場感と、相手に喜んでもらえるお返し品の選び方をお伝えします。
私も最初は相場が分からず、先輩ママ友に何度も相談しました。
経験を積んで分かったコツもお教えしますね!
贈り物の金額別お返しの相場一覧
初節句のお返しの基本的な考え方は、いただいたお祝いの金額の1/3から1/2程度が目安とされています。
でも、これはあくまで目安なので、関係性や状況に応じて調整することが大切です。
以下に、いただいたお祝い金額別のお返し相場をまとめてみました。
| いただいたお祝い金額 | お返しの相場 | おすすめのお返し品例 |
|---|---|---|
| 3,000円〜5,000円 | 1,000円〜2,000円 | お菓子詰め合わせ、タオル |
| 5,000円〜10,000円 | 2,000円〜3,500円 | 和菓子、洋菓子セット |
| 10,000円〜30,000円 | 3,500円〜10,000円 | カタログギフト、商品券 |
| 30,000円以上 | 10,000円〜15,000円 | 高級品、体験ギフト |
ただし、祖父母からの高額なお祝いについては、少し考え方を変える必要があります。
友人の場合ですが、義理の祖父母から50万円相当の雛人形をいただいたと聞きました。
ビックリしましたが、この場合、相場通りだと15万円以上のお返しが必要になってしまいますが、それは現実的ではありませんよね。
祖父母へのお返しは、金額よりも感謝の気持ちが伝わるものを選ぶのがポイントです。
例えば、
- 子どもの写真を使ったフォトブック
- 手作りの感謝状やメッセージカード
- 祖父母が好きな老舗の和菓子や名産品
- 初節句の食事会への招待(これも立派なお返しです!)
年齢や関係性別の適切なお返し品の選び方
お返し品を選ぶ時は、相場だけでなく、相手の年齢や関係性、好みを考慮することが大切です。
同じ金額でも、相手によって喜ばれるものって全然違いますからね!
祖父母(60代以上)への選び方:
祖父母世代には、伝統的で上品なものが喜ばれる傾向があります。
私の経験では、老舗の和菓子や銘茶、高級な海苔などの食品ギフトが特に好評でした。
また、孫の成長を感じられるものも素敵ですね。
- 老舗の和菓子詰め合わせ
- 高級お茶セット
- 季節の果物(高級フルーツ)
- 子どもの写真付きカレンダー
- 伝統工芸品(湯呑み、箸など)
親世代(40〜50代)への選び方:
親世代は実用性を重視する方が多いので、日常使いできるものや、ちょっとした贅沢を感じられるものが人気です。
私の姉にカタログギフトを贈ったところ、「自分では買わないような良いものが選べて嬉しい」と言ってもらえました。
- カタログギフト
- 商品券(百貨店、Amazon等)
- 高級洋菓子セット
- ブランド品(タオル、食器等)
- 体験ギフト(レストラン、エステ等)
若い親戚(20〜30代)への選び方:
若い世代には、トレンド性のあるものや、SNS映えするような見た目の可愛いものも喜ばれます。
いとこへのお返しで選んだおしゃれなお菓子セットは、インスタに投稿してもらえて嬉しかったです!
- おしゃれなスイーツ
- 話題のブランドのお菓子
- コーヒーギフトセット
- 入浴剤・バスソルトセット
- プリザーブドフラワー
喜ばれるお返し品ランキングと避けるべき品物
これまでの経験と、ママ友たちとの情報交換から分かった、実際に喜ばれるお返し品をランキング形式でご紹介します!
逆に、「これは失敗だった…」という品物も正直にお伝えしますね。
喜ばれるお返し品TOP5:
- カタログギフト – 相手が自分で選べるので間違いなし!
- 老舗の和菓子・洋菓子 – 上品で消費できるのが◎
- 商品券 – 実用性抜群、使い勝手が良い
- 高級タオルセット – 日常使いできて長く愛用してもらえる
- 季節の果物・グルメギフト – 特別感があって美味しい
一方で、避けた方が良い品物もあります。
私も実際に失敗した経験があるので、参考にしてくださいね。
避けるべきお返し品:
- 刃物類 – 縁起が悪いとされることがある
- ハンカチ – 「手切れ」を連想させるため
- 櫛(くし) – 「苦」「死」を連想させる
- 時計 – 「時間を気にしろ」という意味に取られる場合も
- 好みが分かれる食品 – アレルギーや好き嫌いがある
- 安っぽく見える品物 – 感謝の気持ちが伝わりにくい
私が一番失敗したのは、義理の叔母に珍しい健康茶を贈った時です。
「健康に気を遣え」という意味に取られてしまい、気分を害してしまいました。
相手の状況や性格を考慮することの大切さを痛感しましたね…
迷った時は、消耗品で上品なものを選ぶのが一番安全です。
食べ物やタオル、入浴剤などは、好みに関わらず使ってもらえるので失敗が少ないですよ!
初節句お返しの最適な時期とタイミング

お返しの時期って意外と重要なポイントなんです。
早すぎても遅すぎても、相手に不自然な印象を与えてしまうことがあります。
私も最初は「いつお返しすればいいの?」と悩みました。
ここでは、適切なタイミングと、万が一遅れてしまった場合の対処法もお教えします。
また、雛祭りと端午の節句で微妙に違いもあるので、そのあたりも詳しく解説しますね!
お返しを渡すべき期間と遅れた場合の対処法
初節句のお返しは、初節句の行事が終わってから1ヶ月以内が基本的なマナーとされています。
つまり、3月3日の雛祭りなら4月3日頃まで、5月5日の端午の節句なら6月5日頃までが目安ですね。
ただし、実際には以下のような流れが理想的です。
| タイミング | 推奨期間 | ポイント |
|---|---|---|
| お返しの準備 | 初節句の2週間前 | 慌てずに品物を選べる |
| お返し配送・手渡し | 初節句から1〜2週間後 | 相手の記憶に新しいうちに |
| お礼の連絡 | 初節句当日〜3日以内 | まずは電話やメールで感謝を |
私の場合、長男の初節句の時は準備が遅れてしまい、初節句から3週間後にお返しをしました。
その時は、お返しと一緒に「お返しが遅くなり申し訳ございませんでした」という一言を添えたメッセージカードを同封しました。
もしお返しが遅れてしまった場合の対処法
- まず電話で直接お詫びをする
- お返し品に謝罪の気持ちを込めた手紙を添える
- 通常より少し良いもの・高価なものを選ぶ
- 直接お会いしてお渡しする機会を作る
実際に私の友人で、初節句から2ヶ月後にお返しをした方がいました。
その時は、季節の良い時期だったので、直接お宅にお伺いして、お詫びと一緒にお返しをお渡ししたそうです。
誠意を見せることで、相手にも理解してもらえたと言っていました。
ちなみに、お返しが半年以上遅れてしまった場合は、初節句のお返しとしてではなく、「心ばかりの品」として改めてお渡しするのが良いでしょう。
その際は、初節句のお返しが遅れたことを素直に謝罪し、別の機会(お中元やお歳暮の時期など)にお渡しするのがスマートです。
節句の種類別(雛祭り・端午の節句)のお返し時期
実は、雛祭りと端午の節句では、お返しの時期に微妙な違いがあるんです。
私も娘と息子、両方の初節句を経験して初めて気づいたポイントです!
雛祭り(3月3日)の場合:
雛祭りのお返しは、3月中に済ませるのが理想的です。
なぜかというと、4月に入ると新年度が始まり、みなさん忙しくなるからなんです。
私の経験では、3月中旬頃にお返しをお渡しすると、相手も落ち着いて受け取ってもらえました。
- 最適期間:3月10日〜3月25日頃
- 遅くとも:4月上旬まで
- おすすめ:春らしいお花見季節に合わせた品物
- 注意点:年度末の忙しい時期を避ける
端午の節句(5月5日)の場合:
端午の節句のお返しは、ゴールデンウィーク明けから5月中旬頃が良いタイミングです。
ゴールデンウィーク中は旅行などで不在の方も多いので、連休明けを狙うのがポイントですね。
- 最適期間:5月10日〜5月25日頃
- 遅くとも:6月上旬まで
- おすすめ:初夏らしい爽やかな品物
- 注意点:ゴールデンウィーク中の配送は避ける
私の実体験では、息子の端午の節句の時、ゴールデンウィーク中にお返しを送ってしまい、受け取りが大変だったという連絡をもらいました。
それ以来、連休中の配送は避けるようにしています。
また、どちらの節句でも共通して言えるのは、季節感を大切にするということです。
雛祭りなら桜の季節、端午の節句なら新緑の季節を意識した品物選びをすると、より喜んでもらえますよ!
お返しと一緒に添える挨拶状・メッセージの書き方
お返し品だけでなく、心のこもったメッセージを添えることで、感謝の気持ちがより伝わります。
私も最初は何を書けばいいか分からず、ネットで例文を調べましたが、やはり自分の言葉で書いた方が気持ちが伝わりますね。
基本的な挨拶状の構成:
- 時候の挨拶
- お祝いへのお礼
- 子どもの近況報告
- お返しの品についての説明
- 今後のお付き合いのお願い
- 結びの挨拶
雛祭りのお返しメッセージ例:
桜の便りが聞かれる季節となりました。
先日は○○の初節句に際し、立派なお雛様をいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、○○も元気に成長し、初めての雛祭りを家族みんなで楽しく過ごすことができました。
心ばかりの品をお送りさせていただきましたので、ご笑納ください。
今後とも、○○の成長を温かく見守っていただければ幸いです。
季節の変わり目ですので、どうぞお体にお気をつけください。
端午の節句のお返しメッセージ例:
新緑が美しい季節となりました。
この度は○○の初節句にお心遣いをいただき、ありがとうございました。
いただいた兜飾りは、○○の成長を願う皆様のお気持ちと共に、大切に飾らせていただきました。
ささやかですが、お礼の気持ちを込めて心ばかりの品をお送りいたします。
○○も日々たくましく成長しており、皆様に支えられていることを心から感謝しております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
メッセージを書く時のコツ:
- 子どもの様子を具体的に書く(「笑顔が増えました」「寝返りができるようになりました」など)
- 写真を同封する場合は、メッセージでも触れる
- 相手との関係性に応じて、敬語の度合いを調整する
- 手書きで書くと、より気持ちが伝わる
私が特に心がけているのは、子どもの成長エピソードを入れることです。
「いただいたお雛様を見て、手をバタバタと動かして喜んでいました」といった具体的な様子を書くと、相手も微笑ましく感じてもらえますよね!
初節句お返しでよくある失敗例と成功のコツ

最後に、実際によくある失敗例と、それを避けるための成功のコツをお伝えします。
私自身の失敗体験や、ママ友たちから聞いた「やってしまった…」エピソードも含めて、正直にお話ししますね。
これを読んでおけば、同じような失敗を避けられるはずです!
特に親戚関係は一度こじれると修復が大変なので、事前に対策を知っておくことが大切ですよね。
親戚関係を悪化させるNG行為と注意点
初節句のお返しで親戚関係がギクシャクしてしまうのは、本当に避けたいですよね。
私も実際に経験した、またはママ友から聞いた「これは失敗だった」というNG行為をご紹介します。
最も危険なNG行為TOP5:
- お返しを全くしない・忘れる
これは私の友人の実体験ですが、忙しさにかまけてお返しを忘れてしまい、半年後に義理の姉から「お返しはいただけないんでしょうか?」と連絡が来て、非常に気まずい思いをしたそうです。 - 明らかに安い・適当な品物を選ぶ
5万円の五月人形をいただいたのに、500円のお菓子だけお返しした方がいました。相手から「感謝されていないのかな」と思われてしまい、その後の関係がぎこちなくなってしまいました。 - 相手の好みを全く考慮しない品物選び
アルコールが飲めない方にワインギフトを、甘いものが苦手な方にケーキをお返しした例があります。事前に好みを確認するか、無難な品物を選ぶべきでした。 - お返しの時期が極端に遅い
私の知人で、初節句から4ヶ月後にお返しをした方がいます。相手から「もう忘れていたのに…」と言われ、かえって印象を悪くしてしまいました。 - 同じ親戚内で明らかに差をつける
兄弟でいただいたお祝いが同程度なのに、お返しの内容に大きな差をつけてしまい、家族間でトラブルになったケースがあります。
避けるべき態度や行動:
- お返しについて相談もせず、独断で決めてしまう
- 「お返しなんて面倒」という態度を見せる
- メッセージなしで品物だけ送る
- 相手からの連絡を無視する
- お返し品の値段を相手に聞かれて正直に答えてしまう
私が一番印象に残っている失敗談は、義理の姉へのお返しで起きました。
同じ品物を複数の親戚に送ったのですが、たまたま親戚同士が集まった時に「同じものをもらった」という話になり、「手抜きをされた」と感じられてしまったんです。
それ以来、同じ親戚グループには違う種類の品物を選ぶように気をつけています。
予算オーバーを防ぐお返し計画の立て方
初節句のお返しって、思った以上にお金がかかることがありますよね!
私も最初の計画では3万円の予算だったのに、最終的に8万円もかかってしまった経験があります。
そこで学んだ、効率的な予算計画の立て方をお教えしますね。
予算計画の基本ステップ:
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1. リストアップ | お祝いをくれた方全員を書き出す | 漏れがないよう夫婦で確認 |
| 2. 分類 | 関係性・いただいた金額で分ける | 3〜4つのグループに分類 |
| 3. 予算設定 | 各グループの予算上限を決める | 総額の上限も設定する |
| 4. 商品選定 | 予算内で品物を選ぶ | 送料・包装代も考慮する |
実際の予算計画例(私の体験より):
- Aグループ(祖父母):5,000円×4人=20,000円
- Bグループ(叔父・叔母):3,000円×6人=18,000円
- Cグループ(いとこ等):2,000円×4人=8,000円
- 送料・包装代:約5,000円
- 合計:51,000円
でも実際は、「この人にはもう少し良いものを…」と思って予算オーバーしがちなんです。
そこで私が編み出した予算オーバー防止のコツをご紹介します。
コツ1:まとめ買いを活用する
同じお店で複数購入すると割引があったり、送料が無料になったりします。私は楽天のお気に入りショップで、タイムセール期間中にまとめて購入して、2万円近く節約できました!
コツ2:季節の終わりを狙う
母の日ギフトの時期が終わった後や、お中元商戦が終わった後は、同じような商品が安くなることがあります。時期をずらせる場合は、この方法もおすすめです。
コツ3:手作り要素を加える
市販の品物に、手作りのメッセージカードや子どもの写真を添えることで、高価でなくても特別感を演出できます。私はフォトブックを手作りして、大変喜ばれました!
予算を抑えながら満足度を上げるアイデア:
- 地域の特産品を直接取り寄せる(中間マージンがない)
- ふるさと納税の返礼品を活用する
- 季節のイベント(母の日、父の日)と合わせる
- 兄弟・親戚と合同でお返しを贈る
- 体験ギフト(食事券など)で印象に残るものにする
遠方の親戚へのお返し配送方法と梱包のマナー
最近は遠方にお住まいの親戚も多いですよね。
私も北海道と沖縄に親戚がいるので、配送でのお返しは何度も経験しています。
直接会えない分、梱包や配送方法により一層気を遣う必要があるんです。
配送時期の選び方:
遠方への配送では、到着日時の調整が重要です。
私が失敗したのは、お盆の時期に冷蔵便で送ってしまい、親戚が旅行中で受け取れず、商品が傷んでしまったことです。
- 避けるべき時期:年末年始、お盆、ゴールデンウィーク
- おすすめ時期:平日の午前中指定
- 事前連絡:配送の2〜3日前に到着予定を連絡
梱包のマナーとコツ:
| 梱包要素 | ポイント | 注意事項 |
|---|---|---|
| のし | 「内祝い」または「初節句内祝い」 | 子どもの名前を入れる |
| 包装 | 上品で季節感のある包装紙 | 派手すぎず、地味すぎず |
| 緩衝材 | 割れ物は十分に保護 | 開封しやすさも考慮 |
| メッセージ | 必ず手書きの一言を添える | 配送への謝罪も含める |
配送業者の選び方:
- ヤマト運輸:時間指定が細かくできる、再配達しやすい
- 佐川急便:法人向けサービスが充実
- ゆうパック:全国均一料金でコスパが良い
- 冷蔵・冷凍便:食品ギフトの場合は必須
私が最も気を遣うのは、到着のタイミング調整です。
特に生鮮食品や冷蔵品の場合は、必ず事前に電話で「○日の午前中に到着予定です」と連絡しています。
遠方配送で喜ばれる工夫:
- 地域の名産品を選んで「○○県から心を込めて」というメッセージを添える
- 子どもの写真や手形・足形を同封する
- 到着後にお礼の電話やメールをする
- 季節の便りも一緒に送る
特に私が工夫しているのは、開封する瞬間のことを考えた梱包です。
箱を開けた時に、まず目に飛び込むのが手書きのメッセージカードになるように配置しています。
遠くにいても、心は近くにあることを伝えたいですからね!
また、配送後のフォローも大切です。
「無事に到着しましたでしょうか?」という確認の連絡を入れることで、相手に気にかけていることが伝わります。
私の経験では、この一言があるかないかで、相手の印象が大きく変わりますよ。

まとめ
初節句のお返しについて、基本的なマナーから実践的なコツまで、私の実体験を交えながらお伝えしてきました。
初節句のお返しで最も大切なのは、感謝の気持ちを相手に伝えることです。
金額の大小よりも、心を込めて選んだかどうか、相手のことを思いやって準備したかどうかが重要なんですね。
この記事のポイントをもう一度整理すると
- 基本マナー:いただいた金額の1/3〜1/2程度が相場
- 時期:初節句から1ヶ月以内、できれば2週間以内が理想
- 選び方:相手の年齢や関係性、好みを考慮する
- メッセージ:手書きの感謝の言葉を必ず添える
- 配慮:親戚関係を良好に保つことを最優先に
私も最初は分からないことだらけで、不安でいっぱいでした。
でも、相手を思いやる気持ちがあれば、多少の失敗があっても必ず伝わります。
完璧を目指さず、感謝の気持ちを大切に、お返しの準備を進めてくださいね!
お子様の健やかな成長と、皆様の家族の幸せを心からお祈りしています。
素敵な初節句の思い出になりますように!