初節句で迷わない!柏餅お返しのマナー・数・選び方ガイド

初節句と聞くと、「赤ちゃんが元気に育ちますように」と願いを込めて家族みんなでお祝いをする大切な行事ですよね。
その時に欠かせないのが柏餅のお返し。
でも、「数は決まっているの?」「誰に渡すの?」「どんなものを選べばいいの?」と迷う方も多いと思います。
この記事では、初節句における柏餅のお返しの決まりやマナーを、実体験や地域の風習も交えて詳しくご紹介しますね!
初節句の柏餅お返しの重要性と背景

初節句は、赤ちゃんが生まれて初めて迎える大きな節目のお祝いです。
両家の祖父母や親戚からいただいたお祝いに対して感謝を伝えるために「お返し」をするのが一般的なんですよ。
特に柏餅は「子孫繁栄」や「無病息災」の意味を持つ縁起物であり、初節句のお返しにピッタリなお菓子なんです。
単なるお土産ではなく、昔からの風習や家族の絆を大切にする気持ちが込められているのが背景なんですね。
初節句とは?その意味と背景を解説
初節句は、男の子なら5月5日の端午の節句、女の子なら3月3日の桃の節句に行います。
赤ちゃんが無事に生まれ、これから健やかに成長していけるように願う大切な行事ですね。
昔は「乳幼児の生存率が低かった時代」に、子どもの健康を祈る意味で盛大に行われていたそうです。
私も子どもの初節句の時には、両家の祖父母を招いて食事会をしましたが、みんなが「元気に育ってね!」と笑顔でお祝いしてくれたのがとても印象に残っていますよ。
柏餅の役割と初節句における意義
柏餅は、柏の葉で包まれたお餅ですよね。
柏の木は「新芽が出るまで古い葉が落ちない」という特徴があり、そこから「家系が絶えない」「子孫繁栄」という縁起の良さが伝えられています。
だからこそ、男の子の端午の節句に欠かせないお菓子になったんです。
お返しに柏餅を選ぶのは、ただ甘いものを配るというだけでなく、「うちの子が健やかに成長して、家族のつながりが続きますように」という願いを込めているんですよ。
お祝いとお返しの関係性
お祝いをいただいたら、必ずお返しをするべき?と悩む方も多いですよね。
実は初節句では「お祝い=子どもへのプレゼント」と考えられるので、お返しはそこまで堅苦しくしなくても大丈夫なんです。
ただし、いただいた金額や品物が大きい場合は、感謝の気持ちを表すために柏餅や内祝いを贈るのが一般的なマナーですよ。
私の周りでも、「現金でお祝いをいただいたから、内祝いと一緒に柏餅を贈った」というケースが多かったです。
初節句の柏餅お返しの基本

柏餅のお返しといっても、どのくらいの金額が相場なのか、誰にどこまで渡せばいいのか、地域の風習によっても違ってきますよね。
ここでは、基本的な目安をご紹介します。
柏餅お返しの相場について
一般的に、初節句のお返しはいただいたお祝いの3分の1から半額程度が目安とされています。
たとえば、1万円をいただいたら3,000円~5,000円くらいのお返しをするイメージですね。
そこに柏餅を添えることで「季節の縁起物」という意味合いが加わるので、より丁寧なお返しになりますよ。
私も親戚から現金をいただいたときには、デパートでちょっと高級な柏餅を買って、感謝の手紙を添えてお渡ししました。
地域や風習による違い
実は、地域によってお返しの習慣は大きく違います。
関東では柏餅が一般的ですが、関西ではちまきを贈るところも多いんです。
私の友人は関西出身で、「うちは柏餅じゃなくて必ずちまきだよ!」と言っていました。
地域ごとの伝統や風習を大事にするのも、初節句ならではの魅力ですよね。
どこまでお返しが必要か?親戚との関係
お返しは「必ずしも全員に渡す必要はない」と言われています。
祖父母などからは「お返しは要らないよ、その分赤ちゃんのために使ってね」と言われることも多いですよね。
ただし、叔父・叔母・親戚などにはちょっとした柏餅セットや菓子折りをお返しすると丁寧です。
関係性や距離感によって変わりますが、迷ったら「感謝を伝える」気持ちを優先するのが一番ですね。
初節句の柏餅お返しのマナー

初節句のお返しは、感謝の気持ちを丁寧に伝えることが大切ですよね。
柏餅や内祝いを贈る際には、水引やのし紙を整え、贈るタイミングや品物選びにも配慮するのが基本です。
近親者には柏餅、遠方の方には日持ちする和菓子や詰め合わせを選ぶなど、相手に喜ばれる工夫をすると、より心のこもったお返しになりますね。
内祝いの基本マナー
初節句のお返しは「内祝い」として贈るのが基本ですよね。
そもそも内祝いとは、いただいたお祝いに対して「ありがとう」という気持ちを伝えるための習慣です。
赤ちゃんが主役のお祝いなので、無理に高額なお返しをする必要はありません。
大切なのは形式よりも、気持ちをきちんと形にすることなんですよ。
内祝いで意識すべきポイントは以下の通りです。
- のし紙は紅白の蝶結びを使用する
- 表書きは「内祝」または「初節句内祝」とする
- 贈る相手の名前ではなく、赤ちゃんの名前を入れるのが一般的
- タイミングは初節句を終えてから1週間以内が目安
私自身も最初の子どもの初節句のとき、「のし紙はどうすればいいの?」と戸惑ったんですが、デパートの和菓子売り場で「初節句用の内祝いに使います」と伝えたら、店員さんが適切なのし紙を用意してくれたので安心しました。
こういうときはプロに相談するのが一番ですね。
贈り物の選び方とタイミング
お返しに選ぶものは、基本的に日持ちするお菓子や縁起物が良いとされています。
特に柏餅は季節限定なので「いかにも初節句らしい」と喜ばれますよね。
ただ、柏餅は日持ちが短いので、贈る相手が遠方の場合は、代わりに和菓子の詰め合わせや焼き菓子を選ぶのもおすすめです。
私が実際にお返しを選んだときは、両親には柏餅、遠方の親戚にはデパートのオンラインショップでカステラや最中の詰め合わせを贈りました。
賞味期限を考えたら、これが一番安心でしたね。
贈るタイミングも重要です。基本的には初節句の食事会が終わってからすぐ、もしくは遅くても1週間以内に渡すのがマナーです。
「お祝いをいただいてから、だいぶ経ってからお返しをした…」となると、どうしても感謝の気持ちが薄れて伝わってしまいます。
準備は事前にしておき、食事会当日に持ち帰ってもらうのもスマートですよ。
選び方のポイントをまとめると:
- 柏餅は近場の親族に(渡せるタイミングが近い場合)
- 遠方には日持ちする焼き菓子やカステラ
- お菓子だけでなく、お茶や紅茶をセットにすると高級感アップ
こうして贈り分けることで、「相手に配慮して選んだ」という気持ちが伝わりますよね。
水引やのし紙の重要性
「のし紙や水引なんて形式的でしょ?」と思う方も多いかもしれませんが、実はとても大切な要素なんです。
内祝いは「きちんと礼を尽くす」ことが第一。
相手がご年配の方なら特に、のしや水引があるかどうかで印象が大きく変わるんですよ。
内祝いに使う水引は「紅白の蝶結び」。
これは「何度あってもよいお祝い」という意味が込められています。
表書きは「内祝」や「初節句内祝」と書き、下段には赤ちゃんの名前を入れるのが一般的です。
こうすることで、「赤ちゃんの成長を祝っていただきありがとうございます」という意味がしっかり伝わるんですよね。
私の体験ですが、ある親戚に内祝いを渡したとき、手渡しの際に「名前が入っていて嬉しいね、記念になるよ」と言われたことがあります。
形式的に見えても、赤ちゃんの名前が印字されたのし紙は、相手にとっても特別な贈り物になるんです。
さらに、包装紙やのしの色合いにも気を配ると印象がアップします。
最近はおしゃれなデザインののし紙や、和モダンなラッピングを選べるお店も増えています。
伝統を守りつつ、少しセンスを加えるのも現代風でおすすめですよ。
おすすめの柏餅とその選び方

柏餅はブランドや地域によって味や見た目が異なり、贈る相手に合わせた選び方が大切です。
有名和菓子店の柏餅や季節限定商品は特別感があり喜ばれますよね。
また、日持ちの短い柏餅は、遠方へのお返しには焼き菓子や詰め合わせとセットにするのがおすすめです。
季節感と縁起物としての意味も大切に選ぶと良いですね。
人気ブランドの柏餅紹介
柏餅と一口に言っても、地域やお店によって味や見た目が大きく違うんですよね。
特にお返し用に選ぶ場合は、ちょっと特別感のあるブランドを選ぶと喜ばれますよ。
例えば老舗和菓子店の「とらや」や「鶴屋八幡」、関東で人気の「舟和」などは、安心感があり贈り物にもぴったりです。
私自身も初節句のお返しで「とらや」の柏餅を選んだのですが、やはり包装から高級感が漂っていて、親戚から「さすがちゃんと選んでくれたね」と言ってもらえたんですよ。
また最近では、有名デパートや百貨店限定の柏餅も人気があります。
デパ地下の和菓子売り場では「限定○○個」「端午の節句限定パッケージ」といった商品が並ぶので、ちょっと特別なお返しを探している方にはおすすめです。
さらに、冷凍便で送れる柏餅も増えているので、遠方の親戚に贈るときにも便利なんですよね。
贈り物は「美味しさ」だけでなく「見た目」や「ブランド力」も大切!
普段はなかなか食べられない有名店の柏餅を選ぶと、それだけでお返しに特別感が出ますよ。
季節の食べ物としての柏餅
柏餅の魅力は、なんといっても「季節を感じられる特別感」ですよね。
普段から食べられるお菓子ではなく、5月の端午の節句の時期にしか出回らないので、贈られる側も「初節句ならではだなぁ」と感じてくれます。
柏餅はもちもちのお餅に、こしあんや粒あん、みそあんなどが入っていて、それを柏の葉で包むことで独特の香りが楽しめるんです。
私は毎年端午の節句の時期になると、必ず和菓子屋さんで柏餅を買うのですが、柏の葉の香りがふわっと広がる瞬間がなんとも言えないんですよね。
だからこそ、お返しに選ぶと「季節を感じる粋な贈り物」になるんです。
ただ注意したいのは、柏餅は日持ちが短いこと。
常温保存で1~2日程度しか持たないことが多いので、相手の都合に合わせて渡す必要があります。
遠方の方には先ほど触れた冷凍タイプや、柏餅に似た雰囲気の和菓子セットを選ぶと安心ですね。
つまり柏餅は、単なるお菓子ではなく「その時期ならではの縁起物」であり、「季節感を贈るギフト」として価値があるんです。
お菓子やギフト「セット」の提案
柏餅単品で贈るのも良いですが、さらに工夫して「ギフトセット」として贈ると喜ばれるんですよね。
例えば、柏餅に日本茶を添えるセットや、和菓子の詰め合わせと組み合わせると一層華やかになります。
私が実際にお返しをしたときには、柏餅と一緒に「新茶」を贈りました。
ちょうど5月は新茶の季節でもあるので、「端午の節句と一緒に初物の新茶もどうぞ」という形にしたら、とても喜ばれたんですよ。
セットにするアイデアをいくつか挙げると
- 柏餅+新茶(季節感たっぷりの組み合わせ)
- 柏餅+和菓子詰め合わせ(遠方にも安心して贈れる)
- 柏餅+紅茶やコーヒー(洋風好きな方におすすめ)
- 柏餅+風呂敷や和小物(記念品感をプラスできる)
贈り物は「食べて終わり」ではなく、「思い出に残る」工夫があるとさらに嬉しいですよね。
柏餅を中心にしながら、ちょっとした心遣いを添えると、相手にとって忘れられない内祝いになるはずです。
両家別々の初節句とお祝い
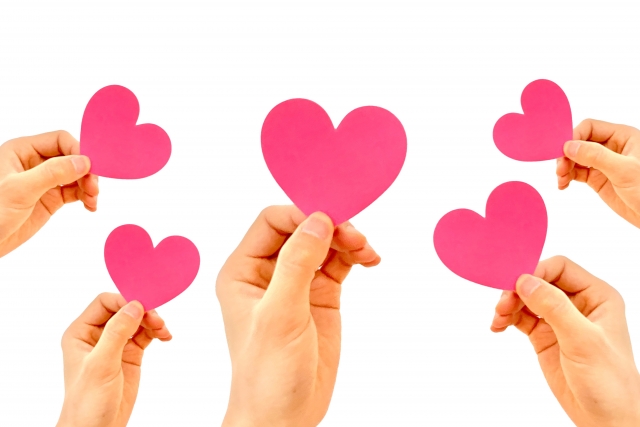
両家で別々にお祝いする場合も、感謝の気持ちを丁寧に伝えることがポイントです。
食事会を行う場合は席順や贈り物のバランスを意識し、会えない場合は手土産や和菓子でお礼を伝えましょう。
祖父母や親戚に喜ばれるよう、赤ちゃんの写真やメッセージを添える工夫も効果的ですよ。
両親を呼ぶ場合の心得
初節句は両家の祖父母を呼んで一緒にお祝いをするケースが多いですよね。
私も子どもの初節句で両親と義両親を招いたのですが、やっぱり両家のバランスを意識することが大切だと感じました。
料理や席順、贈り物など、どちらかに偏らないようにするのがポイントです。
例えば食事会を開くなら、手料理に加えて仕出しやケータリングを利用するのも良いですよ。
準備が大変すぎて親が疲れてしまうのは本末転倒ですからね。
また、お返しも両家で内容をそろえると不公平感が出ません。
「赤ちゃんのお祝いをみんなで楽しむ」という気持ちを大切にするのが一番ですね。
食事会をしない時の手土産選び
最近は「両家が遠方で集まれない」「家庭の事情で大きな食事会はできない」というケースも増えていますよね。
そんなときには、手土産や贈り物で感謝を伝えるのが良いですよ。
柏餅や和菓子はもちろん、季節感のあるフルーツやスイーツもおすすめです。
私の知人は、食事会をせずに「お祝いをいただいた親戚に、少し良い羊羹を贈った」と言っていました。
それでも十分感謝の気持ちは伝わりますし、相手も気を遣わずに受け取れるんですよね。
大事なのは「会えないから何もしない」ではなく、形を変えても気持ちを伝えることなんです。
実家へのお礼の方法
祖父母からは特に大きなお祝いをいただくことが多いので、きちんとお礼をしたいところですよね。
お返しの品は控えめでも構いませんが、「ありがとう」の気持ちをしっかり伝えるのが大切です。
例えば、柏餅や和菓子に加えて、赤ちゃんの写真を添えるととても喜ばれます。
私も実家にお返しを送るときに、手書きのメッセージカードと写真を入れたのですが、「成長の記録が残って嬉しい!」と感激してくれましたよ。
品物よりも「心がこもっているかどうか」が何より大事なんだと実感しました。
まとめ
初節句のお返しは、感謝の気持ちを伝えることが最も大切ですよね。
柏餅は縁起物で季節感もあるので、近場の親族には柏餅、遠方には日持ちする和菓子や焼き菓子を選ぶと喜ばれます。
贈る際には紅白の蝶結びの水引や赤ちゃんの名前入りののし紙を忘れずに添えると、丁寧さが伝わります。
また、手書きのメッセージや赤ちゃんの写真を添えると、より特別感が増します。
形式よりも、相手への思いやりと感謝の気持ちを形にすることがポイントです。
初節句を通して、赤ちゃんの健やかな成長を家族みんなでお祝いしましょう!





