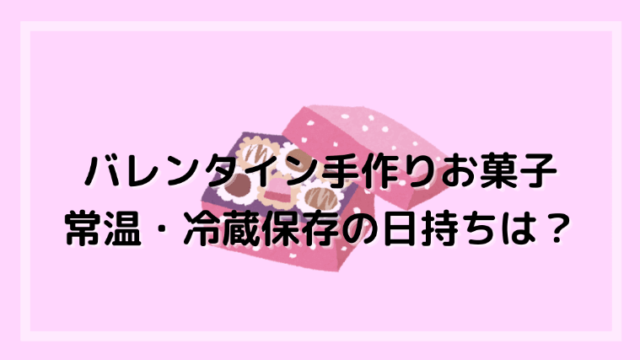義父に父の日プレゼントは必要?あげない選択肢とその理由

父の日が近づくと、毎年悩むのが「義父へのプレゼント、どうしよう?」という問題ですよね。
実のお父さんなら好みも分かりやすく自然に贈れるのに、義父の場合は距離感や関係性によって迷ってしまう人が多いんです。
最近では「無理に贈らず、何もあげない」という選択をする家庭も増えてきています。
そこで今回は、義父に父の日プレゼントをあげない選択の背景や理由、代わりにできる工夫について詳しく解説していきます。
この記事を読めば「贈らないのは失礼?それとも自然なこと?」という疑問もスッキリしますよ。
義父に何もあげない選択とは?

「父の日には必ずプレゼントを贈るもの」と思いがちですが、実は義父にあえて何もあげないという選択をする人も少なくありません。
義父との距離感や関係性、さらには義父自身の「気を遣わなくていい」という言葉が理由になることもあります。
形式的に贈るよりも、自然体な関わり方を大切にしたいという考えから生まれた、この“あげない選択”について見ていきましょう。
義父との関係性を見直す理由
義父との関係性って人によって本当に違いますよね。
普段からよく会う関係なら感謝を込めて贈り物をしたいと思うかもしれませんが、年に数回しか会わない場合や、そもそもあまり話したことがない場合は「無理にプレゼントを贈らなくてもいいかな」と思う人も多いんです。
私も結婚当初は義父に父の日プレゼントを欠かさず渡していました。
でもある年に「気持ちだけで十分だよ、無理しなくていい」と義父に言われてからは、電話で感謝を伝えるだけにしています。
その方が自然体で、お互いに気を遣わずに済むんですよね。
つまり、義父との距離感を尊重して、何もあげない選択をすることも立派な選択肢なんですよ。
義父に贈るプレゼントの面倒くささ
正直、義父へのプレゼント選びってすごく難しいですよね。
実父なら長年一緒に過ごしているので好みも分かりますが、義父の趣味や欲しいものってなかなか把握できません。
それに「外したらどうしよう」というプレッシャーもあります。
例えば、義父はお酒好きだと思って日本酒を贈ったのに、実は健康のために禁酒していた…なんてこともありますよね。
そんなときは「渡さない方が良かったのかも」と思ってしまいます。
無理に頭を悩ませてプレゼントを探してストレスを感じるくらいなら、何もあげないという選択も十分ありなんですよ。
実父と義父、両方の父の日の違い
実父と義父では「父の日」の意味合いが大きく違います。
実父に対しては「育ててくれてありがとう」という思いが自然に湧きますが、義父は「夫を育ててくれた人」という感謝はあっても、実際に一緒に過ごした時間が短いぶん温度差が出やすいんです。
また、夫が自分の父親にプレゼントを贈るのは自然でも、妻が主導で選ぶのは負担に感じることもあります。
だからこそ、「義父には必ず贈るべき」というルールに縛られない考え方が一般的になりつつあるんですね。
義父に渡すギフトの選び方

「それでもやっぱり何か渡したいな」と思う人もいますよね。
どうせなら義父に喜んでもらえるものを贈りたいものです。
ここでは趣味に合った選び方や人気ギフト、予算の目安を紹介しますね。
義父の趣味に合った贈り物
プレゼント選びで失敗しないコツは、義父の趣味に寄り添うことです。
例えば、、、
ゴルフ好き → ゴルフボールや小物
- 読書好き → 人気作家の新刊や電子書籍カード
- お酒好き → 地酒セットやクラフトビール
- 健康志向 → マッサージグッズや健康食品
私の場合、義父が釣り好きだったので釣具店で小物を選んだら、とても喜んで「また一緒に釣りに行こう」と言ってくれたんです。
趣味をきっかけに会話が広がるのも魅力ですよね。
人気の父の日ギフトランキング
調査によると、父の日に人気のギフトはこんな感じです。
- お酒(ビール・焼酎・日本酒)
- 食べ物(うなぎ・お肉・スイーツ)
- 健康グッズ(マッサージ器・サプリ)
- ファッション小物(ネクタイ・靴下)
- 体験型ギフト(温泉・旅行チケット)
やはり「消えもの」が人気ですね。
食べて楽しむ・体験して思い出になるギフトは、義父も気を遣わずに受け取れるんですよ。
予算別!義父へのプレゼントリスト
予算は3,000〜5,000円が相場です。
- 3,000円以内 → ハンカチやお菓子詰め合わせ
- 5,000円前後 → 名入りグラスやブランド食品
- 10,000円以上 → 高級酒や旅行券
高額すぎると逆に気を遣わせるので注意ですね。
私も以前1万円以上のギフトを贈ったら「そんなに気を遣わなくていいよ」と言われました。
やっぱり「ちょっとした気持ち」が大切ですよね。
義父にあげない選択肢の意義

義父に「何もあげない」というと、冷たい印象を持つ人もいるかもしれません。
でも実際には、義父自身が「無理して贈らなくていいよ」と言ってくれるケースも多いんです。
特に年を重ねると「物を増やしたくない」と感じる義父も多く、プレゼントをもらうよりも「電話をもらえるだけで十分」という人もいます。
つまり、プレゼントをあげないのは必ずしも「手抜き」ではなく、義父にとって居心地の良い関係を築くための選択肢でもあるんです。
ここでは「あげない」ことの意味や、そのときの工夫について考えていきましょう。
父の日いらないと言われた時の対処法
義父から「父の日はいらないよ」と言われたことはありませんか?
その場合、本当に贈らない方が喜ばれることもあるんです。
代わりに、電話で感謝を伝えたり、一緒にご飯を食べたりするのも立派なお祝いですよね。
義父へのしおりメッセージの例
プレゼントをあげない代わりに、メッセージを添えるのもおすすめです。
例えば、、、
- 「いつも家族を温かく見守ってくださりありがとうございます」
- 「お体に気をつけて、これからも元気でいてくださいね」
短い言葉でも心に残るのがメッセージの魅力なんですよ。
贈らないことの心理的背景
贈らないことで「関係を軽く保ちたい」「義父に負担をかけたくない」と考える人も多いです。
つまり、あげないのは冷たいのではなく、むしろ優しさの表れとも言えるんですよね。
夫婦間の意見を共有する重要性

義父への父の日対応は、夫婦間でしっかり相談することが大事です。
例えば妻が「贈りたい」と思っていても夫が「いらないと思う」と考えていたら、そこで意見が食い違ってしまいますよね。
父の日は年に一度のこととはいえ、考え方の違いが小さなストレスにつながることもあります。
逆に言えば「うちはこうしよう」とルールを決めておけば、迷わずに済むんですよ。
大切なのは「夫婦で一緒にどうするか決めること」であって、必ず贈るかどうかにこだわる必要はありません。
この章では、夫婦での話し合いの大切さとその工夫について掘り下げます。
義父との関係をどう改善するか
「贈る・贈らない」で迷ったら、まずは夫婦で義父との関係性を振り返るといいですね。
贈らなくても、他の場面で感謝を示せば十分関係は改善できます。
子どもとの会話で見える義父像
子どもが「おじいちゃんに会いたい!」と言うなら、それも義父との距離感を考えるヒントになりますね。
孫との交流は一番のプレゼントだったりするんです。
義父との関係性を深めるためのヒント

父の日を「贈るか贈らないか」だけで考えるのではなく、義父との関係を深めるきっかけにするのもおすすめです。
例えば、プレゼントがなくても「一緒に食事をする」「孫と遊んでもらう」といった体験そのものが最高の贈り物になる場合もあるんですよね。
イベントを通じて義父の好みや価値観を知ることができれば、普段の会話も弾みやすくなります。
義父との関わり方は家庭によって様々ですが、ちょっとした工夫で自然な関係が築けるんです。
この章では関係性を深める具体的なヒントを紹介していきます。
父の日ルールの見直し
「毎年必ずプレゼントを贈る」というルールは一度やめてもいいかもしれません。
お互いが負担にならない範囲で関わることが一番大切ですよ。
義理の家族との関わり方
義父だけでなく、義母や義理の兄弟との関係性も含めて、どうバランスをとるかを考えるとより自然に過ごせますね。
イベントを通じて知る義父の好み
父の日以外のイベントで義父の好みを知っておくと、必要な時に自然とプレゼントを選べますよ。
調査結果から見る父の日に関するデータ

「世間の人はどうしてるんだろう?」って気になりますよね。
実際、父の日に何をしているかは家庭によって本当にバラバラなんです。
プレゼントを贈る人が多数派ではありますが、「何もしない」という選択も珍しくはありません。
むしろ、調査データを見てみると「習慣だからなんとなく贈る」という人も多く、必ずしも強い意識でやっているわけではないんです。
つまり、「義父にあげない」という選択も決して特別ではなく、実際のデータに裏付けられている行動なんですよ。
この章ではアンケートや調査結果をもとに、父の日のリアルな実態を紹介します。
普段の父の日の過ごし方アンケート
ある調査によると、父の日の過ごし方は以下のようになっています。
- プレゼントを渡す:55%
- 一緒に食事:25%
- 何もしない:20%
意外と「何もしない」という人も多いんですよね。
父の日にプレゼントを渡す理由を探る
渡す人の理由は「感謝を伝えたいから」が圧倒的多数!
でも「習慣だから」という声も多いんです。
つまり義父にあげないことも、決して珍しいことではないということですね。
義父との絆を深めるためのコラム

父の日をめぐる話題は、義父との関係だけでなく、家庭全体のルール作りにもつながるんです。
「母の日にはプレゼントしたのに、父の日はスルー?」という声もありますが、実際にはそのバランスをどうとるかが大事なんですよね。
家庭ごとにルールを決めておけば、お互いに無理なく、かつ気持ちよく父の日を迎えられるんです。
また、母の日と父の日を並べて考えることで「うちの家族にとって感謝を伝える日とは何か」を見直すきっかけにもなりますよ。
この章ではちょっと視点を変えて、義父との絆を深めるためのコラムをお届けします。
母の日と父の日の関連性
母の日にはプレゼントを渡すけど、父の日は忘れられがち。
実はそれも普通のことなんです。
大切なのは形式より気持ちですね。
自分たちの家庭のルール作り
「うちは義父には何もあげない」と決めてしまうのも一つの方法です。
家庭ごとのルールがあれば悩まずに済みますよ。
プレゼント選びのためのコミュニケーション

義父へのプレゼントは、モノそのものよりも「どう渡すか」「誰と一緒に準備するか」が大事なんです。
例えば、子どもと一緒に作った手紙や工作は、どんな高価な品よりも喜ばれることがあります。
義父にとっては「自分を思ってくれる気持ち」が一番のプレゼントなんですよね。
そのためには日頃から義父との会話を大切にして、ちょっとした好みや話題を拾っておくのがポイントです。
この章では、プレゼント選びを支えるコミュニケーションの重要性についてお話しします。
子供と一緒に選ぶ父の日の特別な贈り物
子どもと一緒に手作りカードを作るだけでも十分特別です。
お金をかけなくても心が伝わるんですよ。
義父との会話を欠かさない重要性
日頃から義父とちょっとした会話を重ねておくと、プレゼントに迷わなくなります。
「最近何が好きなんですか?」と聞くだけでも関係はぐっと良くなりますよね。
まとめ
義父に父の日プレゼントを「あげない」という選択は決して間違いではありません。
むしろ、関係性や義父の性格を考えて柔軟に対応する方が自然なんですよね。
もちろん贈りたい気持ちがあるならプレゼントを渡すのも素敵です。
大事なのは形式ではなく気持ち。
感謝の言葉や、ちょっとした会話、子どもを通じた交流こそが一番の贈り物かもしれませんね。